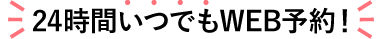千葉県松戸市の松戸ありす歯科

当院は新松戸駅から徒歩7分の場所にある歯医者です。ダイエー新松戸店隣のエムフォレスト4Fに入っております。駐車場は10台ございますが、当院の提携しているタイムズの駐車場をご利用の場合は診療時間に応じて駐車券をお渡しします。
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 -12:00 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | × |
| 14:00 -19:00 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | × |
| 9:00 -13:00 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | × |
| 14:00 -18:00 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | × |
松戸ありす歯科の特徴
広いキッズスペース
松戸ありす歯科ではお子さまにとって歯医者が楽しい場所になるよう、広いキッズスペースをご用意しております。おもちゃも充実させておりますので、待ち時間も退屈せずお待ちいただけます。

ゆったりとした待合スペース
松戸ありす歯科の待合スペースは椅子が一つ一つ独立しておりますので他の患者様とのスペースを空けてゆったりとお待ちいただけます。

土日も診療で通いやすい
松戸ありす歯科は、平日は19時まで(水曜は18時まで)、土日は18時まで診療を行っております。

こどもとママの歯の相談室®
0歳のお子様でも安心して通える歯医者を目指しています。日々の歯磨きのアドバイス、発音や歯並びの悩み、むし歯の予防と治療など幅広いお悩みに対応しております。
お子様の口元の健康について悩んでいるお母さん、お父さん、どうか一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
特設Webサイトはこちら

歯科医師紹介

アクセス
車でお越しの方
駐車場(10台)をご利用いただけます。 また、当院の提携しているタイムズの駐車場をご利用の場合は診療時間に応じた駐車券をお渡ししております。
公共交通機関でお越しの方
新松戸駅から
新松戸駅より徒歩7分です。

お問い合わせ
| 名称 | 松戸ありす歯科 |
|---|---|
| 診療時間 | 月・火・木・金 9:00-12:00 / 14:00-19:00 水・土・日 9:00-13:00 / 14:00-18:00 祝 休診 |
| 住所 | 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸3丁目135 エムフォレスト4F |
| 電話番号 | TEL: 047-700-5514 |
-



ご予約
さくら会ではなるべく患者様をお待たせしないよう、ご予約優先制となっております。
ネット予約は初診の方限定です。
-



来院
初診の方は問診票記入の為にご予約時間より10?15分程度早くご来院をお願いしております。 また、保険証・医療券・お薬手帳などをお持ちいただき、受付にてご提示ください。
-



カウンセリング
最初は現在お口の気になる症状などを担当スタッフがお聞きいたします。お悩みやご相談がある方はお気軽にご相談ください。伺ったお話をもとに治療計画を作成いたします。
-



診療
初めての方は、まずレントゲン撮影と検診を行います。 その後、衛生士による口腔内のお掃除をさせていただく場合もあれば、痛みや腫れがある場合は症状が和らぐよう処置をさせていただく場合もございます。
-



お会計
処置終了後、そのまま次回のご予約をお取りします。新しい診察券をお渡しいたしますので、次回はそちらを受付までお持ちください。お会計を受付もしくは自動精算機で済ませてお帰りください。
-

愛知・春日井
エクボスタイルKASUGAIとなり
さくら歯科
-

愛知・春日井
イオン春日井店内
たんぽぽ歯科
-

愛知・春日井
マックスバリュ春日井坂下店隣
ありす歯科
-

愛知・春日井
エクボスタイルKASUGAI店内
春日井きらり歯科
-

千葉・松戸
ダイエー新松戸店となり
松戸ありす歯科
-
愛知・日進
プライムツリー赤池店内
日進赤池たんぽぽ歯科
-

愛知・春日井
バロー勝川店となり
春日井アップル歯科
-

愛知・名古屋
マックスバリュ鳴子店前
さくら医院 歯科フロア
-

愛知・名古屋
マックスバリュ鳴子店前
さくら医院 医科フロア
-

神奈川・金沢
金沢文庫駅すぐ
金沢さくら医院
-

千葉・流山
流山おおたかの森FLAPS内
流山ハピネス歯科
-

愛知・春日井
イーアス春日井2階
イーアス春日井歯科
-

愛知・名古屋
マックスバリュ太閤店向かい
名駅さくら医院・
名古屋歯科 -

愛知・名古屋
マックスバリュ太閤店向かい
名駅さくら医院・
名古屋歯科(皮膚科) -

東京・大田区
JR大森駅より徒歩4分
きらり大森歯科
-

千葉・流山
COTOE流山おおたかの森内
クローバー歯科
-

千葉・流山
ハナミズキテラス3階
流山ありす歯科・矯正歯科